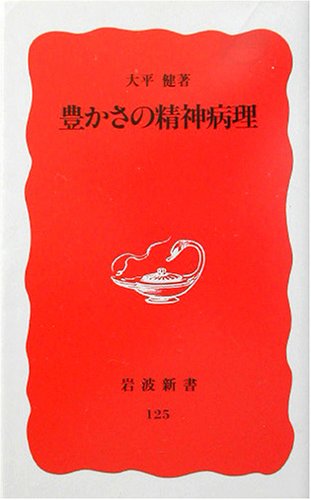刺激的なタイトルの本が出版された。私は心理学者や公認心理師ではなく精神科医だが、この本を読み、いろいろ感じ入ったり思い出したりしたことがあったので紹介してみる……つもりだったのだが、いろいろ考えているうちに後半は個人的な思い出話100%になってしまった。とはいえ個人ブログなので、そのグダグダも含めて書き残してみる。
コロナ禍をとおして浮かび上がる、私たちの心
本書『心はどこへ消えた?』は、週刊誌で2020年春から連載された文章を書籍化したものだという。だからか、コロナ禍によって変化した心とその周辺の問題から話が始まる。
たとえばコロナ禍が始まって以来、私たちはオフラインの会議をせずにオンラインミーティングを使うようになった。コロナ禍ゆえの要請として仕方のないことだったけれども、今までの会議を完全に代替しきっているとはいえない。一例として、この本では「会議が終わった後の廊下の出来事」が挙げられている。
オンラインミーティングにはだいぶ慣れて、結構やれるじゃんと思っているのだが、一向に慣れないのがミーティングの終わり方である。教授会にせよ、研究会にせよ、ゼミにせよ、さっきまで和気藹々と仲良くやっていたのに、「じゃあ、これで終わります」という声と共に、ブチっと画面が消え、自分ひとりの部屋に放り出される。これが切ない。
(中略)
廊下が足りていない。教授会の終わりに、「今日もあの教授のカラオケ状態でしたね」とか「マラカス鳴らそうかと思ってたぜ」とか、廊下で愚痴りあうのが楽しかった。雑談も陰口も全部廊下での出来事だった。事件は会議室でも現場でも起こるのだけど、人間らしいことは大体廊下で起こっていたのである。
従来の、オフラインの会議では、ブチッと会議が終わらない。会議室から廊下に出て、歩いてゆく間にいろいろな意見交換が発生する。会議とそうでない状態の中間でしか語られないことがあるとも言えるし、会議モードから心を切り替えるための中間の空間と時間があるとも言える。
ところがオンラインミーティングには、この、廊下に相当する中間の空間や時間がない。ブチッと画面が消えてしまうから、中間でしか語られないことは語られないし、心を切り替えるための猶予もない。会議後の心の挙動は、オフラインのソレとは違ったものとならざるを得ない。
もうひとつ。《雑談賛歌》というタイトルの、コロナ対策ガイドラインのもとでの一幕に触れた文章も印象的だった。
ガイドライン警察にとって、雑談は摘発すべきものだ。廊下での立ち話や教室内での私語、食堂でのおしゃべり。それらは本来学生生活の一番楽しい部分のはずなのだが、警察目線になると感染リスクを高める不要不急のものにみえてしまう。
(中略)
雑談とは三密の不透明なドサクサのなかで生まれ、育つものだ。そして、そういうものは今、監視され、管理され、清潔にされなくてはならない。感染予防とはすなわち雑談予防なのだ。だけど、本来大学とは雑談がはびこる不潔な空間であったではないか。つまり、ガイドラインやカリキュラムから脱線できることこそ、大学の魅力だったと思うのだ。
このように記したうえで筆者の東畑先生は、2020年の秋に新入生が初めて集まった時のことを以下のように記している。
しかし突然、「キャー!」と黄色い声が上がる。なんだ、どうした、と学生の方を見ると、ひとりの女の子が別の子にぎゅっと抱き着いている。「こんな顔だったんだ!超かわいい!会いたかったー!」抱き着かれた子も嬉しそうにぴょんぴょん跳ねる。「私も超会いたかったよ!」そこからは大騒ぎだった。そこかしこで雑談が大爆発したのだ。この半年、直接会ったことはないけれど、SNSでは繋がっていた彼女たちは、やっと会えたことに興奮して、はしゃぐ。手を握り、抱き着き、大声で笑う。マスクの下で飛沫がキラキラと輝く。
(中略)
大学に雑談が戻ってくる。どんなにガイドラインの目が厳しくても、人と人とが同じ空間にいれば、雑談は花を咲かせてしまう。ガイドラインの隙間に、雑談が生い茂る。それは多分、大学だけじゃない。人は人を怖がったり、嫌いになることもあるけれど、結局人を求めることをやめられない。生身の人間がそこにいる。それだけでわけもなく嬉しくなってしまうのが私たちだと思うのだ。
断っておくと、おそらくこれは2020年秋頃に執筆された内容で、2021年の感染がメチャクチャに広がっていた頃にも東畑先生が同じ風にお考えだったのかはわからない。というのも時期によってコロナ禍の状況は異なるからだ。
さておき、この文章もコロナ禍によって変わってしまった心の周辺事情を象徴している。私たちの心にとって重要・必要だった空間や時間が、感染予防の要請によって制限を被っている。それは仕方のない要請なのだけど、私たちの心にとってノーペナルティーというわけにはいかない。
でもって文中の"雑談の大爆発"が示しているように、それでも人は人を求めずにはいられない。求めかたにも色々あり、一緒に運動や勉強をするのが良い人もいれば宴会が良い人、静かに居場所を共有するのが良い人だっているだろう。どういう形であれ、心はいつまでも自己完結していられるものでなく、他人との繋がりのなかで救われたり傷ついたり変わっていったりしていく。コロナ禍をとおしてそれを再認識した人も多いのではないだろうか。
一介の精神科医から見た『心はどこへ消えた?』
こうしたコロナ禍の話から始まって、『心はどこへ消えた?』は現代社会と現代の心のありようの話に重心を移していく。カウンセリング事例と、不特定多数に当てはまりそうな心の諸問題と、東畑先生自身の経験談とを、行ったり来たりしながら読み進めるようなスタイルだが、緩急のある筆致でそれらが繋がり、各話完結のお話と全体のお話とをなしている。心やカウンセリングに関心のある人には、面白くてたまらない本だと思う。
そうしたうえで、ここからは『心はどこへ消えた?』について一介の精神科医としての感想、または感傷を書いてみる。
まず私は、この本で記されているカウンセリングの描写に懐かしさをおぼえた。というのも、私が精神科医になるかならないかの頃に触れたカウンセリング方面のテキストと、この『心はどこへ消えた?』には、共通する構造があるよう感じられるからだ。
彼女は返事をしなかった。重い沈黙が続いた。傷ついているようでもあるし、何かを考えているようにも見えた。だから聞いた。「何を考えていた?」口が開く。「彼はカウンセリングを壊さないために、私じゃなくて、壁を殴ったんだと思います」私もそう思った。「……なのに、私からカウンセリングを壊してしまうのは良くない、と考えていました」それは彼女が自分の意見を持った瞬間だった。自分の目で見る彼女がいたのだ。だから、伝えた。「ならば、何ができるか一緒に考えましょう」それから彼らは長い道のりを歩んでいくことになった。
たとえばこれは『心はどこへ消えた?』のカウンセリングの一場面だが、こんな具合に、セラピストとクライアントの間で起こった紆余曲折、転機が記される。もちろん転機となる場面だけが記されるのでなく、カウンセリングの導入場面や停滞場面も記されるし、終了に至る過程が記されることも多い。そういうカウンセリングの過程を、私はのどを潤すような勢いで読み進めていった。
職業柄、もちろん私も患者さんの治療過程について日常的に読んだり書いたりしている。しかしそれは心理療法(カウンセリング)の過程、特にここで紹介した過程とは似て非なるものだ。確かに患者さんは治っているし、紆余曲折や転機も記されてはいるけれども、そこには心という問題系は存在しないも同然だ。私が日常的に読み書きしている精神疾患のレジュメでは、症状や行動や認知についてはさまざまに記されているし、環境や関係についてもたくさんの言葉が費やされているが、心という問題系にはたいして踏み込んではいない。
じゃあ、精神科医は心という問題系に昔から踏み込まなかったのか?
そんなことはない。昔はもっと心という問題系に精神科医も踏み込んでいたし、たくさん話題にもしていた。私自身、心という問題系を念頭に置いたレジュメを書き、読んでもいた。病院勤務のカウンセラーとして正真正銘であった、臨床心理士の先生がたのレジュメを読む時だけでなく、精神科医同士のレジュメやディスカッションにも心という問題系はもっとくっきり、頻繁に登場していた。けれども年を追うごとにカルテやレジュメから心という問題系は消えてゆき、かわって、行動や認知についての記述が増えていった。
のみならず、病院勤務の臨床心理士の先生がたのレジュメからも心という問題系についての記述は少なくなり、行動や認知についての記述が増えていったのだった。
現在でも、然るべき場所に行き、然るべき人に耳を傾ければ精神科医が語る心の問題系に触れられないことはない。たとえば精神科医の集まる学会としては最大規模の日本精神神経学会に赴けば、心の問題系に沿った演題を聴聞できる。21世紀以降にクローズアップされた発達障害の患者さんに対し、心の問題系に沿ったかたちでアプローチを試みている精神科医だっている。そういう意味では、心の問題系は死んだわけではないしアップデートされなくなったわけではない。
アップデートといえば、東畑先生のカウンセリングも私の研修医時代(2000年頃)のソレとはイコールではないことは断っておこう。論文集『治療は文化である』のなかで先生は、
「深いところでつながる」「耳を傾ける」「寄り添う」「抱える」「関係を作る」。これらは平成の臨床心理士養成大学院で頻出した常套句である。このような常套句によって治療方針が立てられ、そして「一緒に考えていきましょう」というキラーワードで治療の今後が約束される(上田,2020)。そのような心理療法のことを「平成のありふれた心理療法(以下、HAP*1と省略する)」と呼ぼう。私自身そこで育ち、そしてそこから離れていったわけだが、このHAPがいったい何であったのかを明らかにするのが本論の目的である。
東畑開人『平成のありふれた心理療法 社会論的転回序説』より
……と書きだし、この平成のありふれた心理療法の特徴が「サイコロジカルトーク抜きの心理療法」「ユンギアン化したロジェリアン」であったと解説する。
以上の議論を、河合隼雄とそのフォロワーだけの問題尾に矮小化してはならない。HAPの中核群は確かに「ユンギアン化したロジェリアン」であったが、その本質は「サイコロジカルトーク抜きの心理療法」だったわけで、それはこの時期の他学派においても共通したありようだったからである。
たとえば、河合隼雄と同世代の指導者であった鑪幹八郎も同じ想像力のなかにいた。(中略)あるいは力動学派を離れても同じことがいえる。河合隼雄と並ぶ当時の指導者であった九州大学教授の成瀬悟策が推進していたのは「動作法」である。そこでは身体運動を通じた主体の変容が目指されたわけで、やはりサイコロジカルトークが排されている。そして、当時の東京大学教授の佐治守夫はそもそもロジャース派であった。この時期に指導的立場にあり、その後臨床心理士制度の中核を担った人々は皆「サイコロジカルトーク抜きの心理療法」を教え広めていたのである。HAPが平成に覇権を握っていたとはそういうことである。
東畑開人『平成のありふれた心理療法 社会論的転回序説』より
このように述べたうえで、現代はサイコロジカルトークの時代に変わっていること、HAPが幅をきかせた時代にはHAPが幅をきかせるような社会的環境があったこと等々……が語られていく。このあたりは面白い人にはめちゃくちゃ面白い話だとは思うが、長くなりすぎてしまうので割愛させていただく。
それでも心の問題系から遠ざかるばかりだった私などには、『心はどこへ消えた?』で描かれた心理療法の描写、心に対する機敏は、やっぱり懐かしかった。当たり前かもしれないけれど、東畑先生の本を読んでいると、心という問題系がしっかりそこにあるという安心感がある。他方、いつの間にか私(と私の周囲にある臨床環境)は心の問題系から遠ざかって、症状や行動や認知について語り、それらのフォーマットに基づいたかたちで環境や関係をも語るようになってしまった。その対照を、『心はどこへ消えた?』を読んで私は痛切に思い出した。
でもって、世間においてもある程度そうだったりしないだろうか?
20世紀には、心の問題系は専門家だけのものではなく、多くの人が共有するものでもあった。ここで挙げた大平健『豊かさの精神病理』のような新書がたくさん刷られ、たくさんの人に読まれた。フロイトやユングの名前がメディアに頻繁に登場した時期でもある。小此木啓吾。河合隼雄。木村敏。著名な先生がたが心の問題系を縦横に論じて、専門家ではない人にもそれが届いていた。モノが豊かになったから、次は心を豊かにする番だ──こんな言葉を、あの頃何度耳にしただろうか。
ところが気が付いてみると、心の問題系はどこかへ消えてしまった。いや、消えていないとしても地方の書店の売れ線コーナーに鎮座しているものではなくなった。モノの豊かさが盛期を過ぎて、格差社会が叫ばれるようになった後も決して元には戻らなかった。なお、この点に関しては、東畑先生は前掲の『平成のありふれた心理療法』のなかで
これに対して、ポストHAPが前提としているのは、そういった共同体の解体である。人々をふんわりと包摂していた豊かさは姿を消し、非正規雇用が広がり、誰もが転職、副業、起業を考えてしまう時代になり、個々人はそれぞれでリスクを背負わざるを得なくなった。「モノは豊になったが心はどうか」から「リスクは豊になったが心はどうか」(東畑,2019b)へと時代は変わったのだ。
この時期に心理療法家による文化論も姿を消した。日本的共同性が治療場面で問題になりにくくなったからだろう。その結果、専門家は「先生」と呼ばれてふんわりと依存するに値する対象ではなく、当事者との間で契約に基づいてサービスを提供する対象へと変わった。
私自身も、今では治療場面で「先生」と呼ばれることはかなり少ない。それはもちろん、東京の開業臨床という設定によるものでもあるが(沖縄のクリニックにいたころは私は「先生」であった)、そこでは素朴な「先生転移」は機能せず、治療はサイコロジカルトーク抜きには成立しない。
東畑開人『平成のありふれた心理療法 社会論的転回序説』より
と記しておられる。だとしたら、著名な心理療法家の本が書店に山積みになっていたのも、HAPが覇権を握るような社会環境ならでは、心理療法の専門家が「先生」と呼ばれ、ふんわりと依存の対象とみなされ得る時代ならではだったわけか……。
そしてHAPが終わり、(私の周辺の場合は)心理療法としては認知行動療法が、精神医療としてはDSMなどの操作的診断基準が優勢になっていくなかで、私は"自分にとって懐かしい風景"を見失い、それを『心はどこへ消えた?』という書籍のうちに(多分に勝手に)みていたのかもしれない。
ここで私は言葉を失ってしまった。読み物としてはグダグダになってしまい、おのれの未熟を感じる。すみません。とにかく研修医時代に叩き込まれたことと当時の書店の風景とが次々に思い出されて、胸がいっぱいになってしまっている。
最後にもう少しだけ、私を心の問題系から引き離し、DSM-IV(とDSM-5)という、操作的診断基準に基づいた精神医学へと改宗させた諸先輩について書いておきたい。
もともと私は力動的精神医学が強い環境、つまり精神医学の領域のなかでもHAP的な空気と隣接した環境でキャリアをスタートした。そうした環境だったから、臨床心理士の先生がたの研究会にも何度も参加させていただいた。今よりもずっと心理療法に強い関心を持っていたからでもある。
一方、00年代からはそれに批判的な諸先輩に出会うことが増え、行動や認知や症状にもとづいて患者さんを整理し、筆記するような方法、つまりDSM流の精神医学へと再教育されていった。私の精神科医としての基本フォーマットは、この諸先輩によって与えられたと言って過言ではない。
ところが私にDSM流の精神医学を教えてくれた諸先輩も、それ以前の精神医学、それこそHAP的なもののみなぎる諸々についても結構知っていたのである。彼らは新旧両方をよく知り、新旧両方のやり方の違いをもよく知っていた。そして私の目の前で両者を翻訳してみせたり、翻訳の際に何が削げ落ちてしまうのか、何が余計に加わってしまうのかについて熱心に語った。
心の問題系に最も批判的な先生でさえ、心の問題系の言葉で事物を語るすべを身に付けていたのだ。そのうえで、「シロクマ先生、ちみは、DSM-IVを徹底的に身に付けるのだ」と念押ししたのだった。
けれどもそうした諸先輩のありようを見て私が感じたのは、「DSMは身に付けなければならないが、それ以前の精神医学、それこそHAP的なものを知っておくことは無意味ではない」だった。むしろ諸先輩が偉大なのは、操作的診断基準に基づいた精神医学を修めていること自体ではなく、それ以前の精神医学もよく知って、両方を往復できることに由来しているのではないかと思えてならなかった。今でもそう思っている。私は彼らにならいたい。
幸い、さきにも述べたとおり、日本精神神経学会の会場では今でも心の問題系に沿った演題が聴聞できるし、『心はどこへ消えた?』のような書籍に出会う機会だってある。私のような人間にとって、これはありがたいことだし、これからも追いかけていきたいと思う。職業人としての私は操作的診断基準に頼りきっているけれども、心という問題系を忘れることはないだろう。