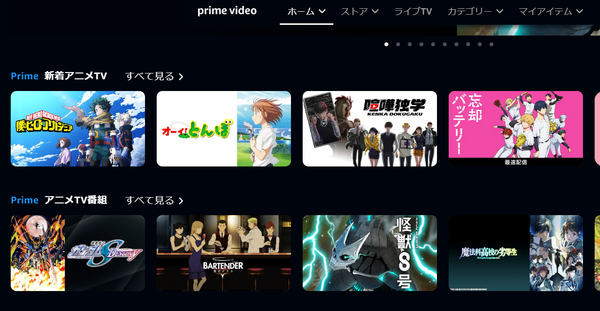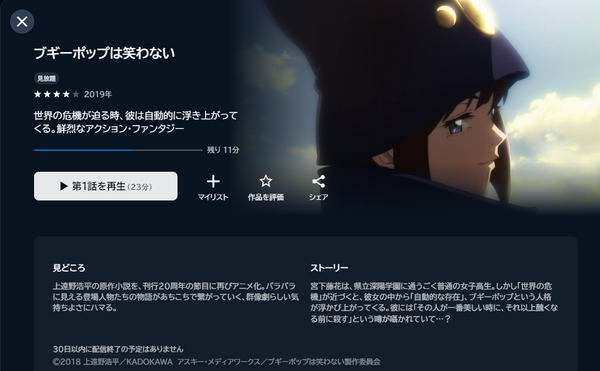news.denfaminicogamer.jp
リンク先は、ファミ通のサイトにアップロードされた、初代『ファイナルファンタジー』(ピクセルリマスター版)の記事だ。タイトルに"実はSFだった(?)"的なことが書かれているためか、はてなブックマークには賛否さまざまな声があがっていた。
私はどこまでSFでどこからがファンタジーなのか、定義づけには興味がない。ただ、1987年に実際にファイナルファンタジーをとおして体験したのは純ファンタジー風の体験からそうではない体験に変わっていくもの、少なくとも『ドラゴンクエスト』や『ハイドライド』や『ザナドゥ』とはちょっと違った趣向だった。
これも機縁、楽しくてしようがなかった初代ファミコン版『ファイナルファンタジー』の楽しかったところを書き残してみる。
思い出話の前に:『ファイナルファンタジー』が発売された頃の時系列
ファミコン版『ファイナルファンタジー』の思い出話をする前に、当時、ゲーム小僧たちが置かれていた国産ロールプレイングゲーム(以下RPGと表記)の時系列に触れておきたい。
ファミコン版の『ファイナルファンタジー』が登場したのは1987年。この時点でRPGは大学生や一部のマニア・オタクだけのものではなく、地方のゲーム小僧にも十分すぎるほど知られた存在となっていた。ファミコン版だけ見ても、1986年にはあの『ドラゴンクエスト』の初代が発売されているし、同年にはファイナルファンタジーをリリースしたスクエアも『ディープダンジョン』を発売している。
で、『ファイナルファンタジー』が登場するのは1987年で、この年はたいへん豪華だった。というのも、この『ファイナルファンタジー』に加え、『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』もファミコン版『ウィザードリィ』も『女神転生』もリリースされたからだ。ファミコン版『ウルティマ 恐怖のエクソダス』が発売されたのも1987年。
当時はPC版のRPGも地方の小中学生にまずまず知られていた。アクションRPGと位置付けられるかもだが、『ザナドゥ』や『イース』は私もプレイしたことがあったし、1987年末には『ソーサリアン』も発売されている。初代『ファイナルファンタジー』がファミコン版として発売されたのは、そうやってRPGが子どもの間で知られ、コンピュータゲームの王道的立ち位置をまさに固めていくような時代だった。
なお、アーケードゲームでは当時は未だシューティングゲームがメジャーだった時期で、『ダライアス』や『R-TYPE』の初代がリリースされている(これはこれで豪華な話ではある)。対戦格闘ゲームはまだ登場しておらず、『ストリートファイターII』の前身、特殊筐体の初代『ストリートファイター』がリリースされている。
はじめ、『ファイナルファンタジー』は『D&D』っぽいゲームとして現れた
初代『ファイナルファンタジー』の美点はいくらでもあるし、冒頭リンクにもたくさん記されている。たとえばガーランドを倒して橋を渡った時に表示される「オープニング画面」には私も圧倒された。
勿論それだけじゃない。良かった点、魅了された点は本当に色々あるのでそれを挙げていきたい。
ひとつには『D&D』*1っぽいゲームシステム。ここでいう『D&D』っぽいとは、魔法の使用回数がレベルごとに回数制であることや、D&D準拠なモンスターが登場することにとどまらない。『ファイナルファンタジー』の『D&D』っぽさは、攻撃の命中判定やダメージ判定にもあらわれている。『ドラゴンクエスト』が比較的揺れ幅の小さなダメージ判定になるのに対し、『ファイナルファンタジー』、特にその序盤ではダメージ判定が大きく揺れる。その揺れ具合が『D&D』っぽくて、ゲーム小僧である私には「ダイスを振っているみたいで本格的」と感じられた*2。
でも、ダメージ判定が大きく揺れるRPGは、えてして遊びにくい。ところが『ファイナルファンタジー』はそうでもなかった。レベルが上がり、前衛職の攻撃回数が増えていくと「2回ヒット」「3回ヒット」といった具合に複数回ヒットするようになり、結果的にダメージの平均値が均されていく。魔法も割と問題ない。『ファイナルファンタジー』は当時のRPGのなかでは属性攻撃ダメージがきっちり通るゲームで、炎に弱いモンスターにファイア系魔法をかけた時や水棲モンスターにサンダー系魔法をかけた時のダメージのとおりが爽快だった。対アンデッド専門魔法であるディア系もそれに準じていて、アンデッドの大群は倒しやすかった。
それから魔法。ファイナルファンタジーの白魔法と黒魔法は、初代の段階では『D&D』のクレリック魔法とマジックユーザー魔法にかなり似ていた。ゲームに欠かせないケアル系魔法やレイズ系魔法だけでなく、プレイヤーにはほとんど使ってもらえないダクネスやスタン、インビジビリティやシールドが元ネタとおぼしきインビジやプロテスなど、脇役魔法も『D&D』に似ていた。『D&D』に似ている度合いは先行国産RPGと比べて顕著で、ひょっとしたら後々に発売される国産RPGと比べても顕著かもしれない。多少なりとも『D&D』をかじっていた私たちには、『ファイナルファンタジー』は『D&D』っぽいゲームをファミコンで遊ばせてくれるもの、それも上級ルールセット*3に登場する魔法すら使わせてくれるものでもあった。
でもって、モンスター。今にして思えばヤバいほど『D&D』っぽかった!
もちろん完璧に『D&D』とは言えないのだけど、パイレーツが登場し、オーガが登場し、ゾンビやスケルトンやシャドウが登場し、さらにそれらの上位・上級モンスターが登場するさまは『D&D』っぽかった。物議をかもした『D&D』のオリジナルモンスター、あのビホルダーもファミコン版には堂々と登場する。
天野喜孝のモンスターデザインがそれに拍車をかける。ちょうどファミコン版『ウィザードリィ』のモンスターデザインが当時のゲーム小僧には「本格派」っぽくうつったのに似て、『ファイナルファンタジー』のモンスターデザインも、これまた「本格派」っぽくうつった。かっこよかったのである。しかもモンスターの攻撃手段や特殊攻撃がじつに『D&D』っぽかった。『D&D』経由で聞きかじった「このモンスターはこうであるはず」という性質を、『ファイナルファンタジー』のモンスターたちはかなり忠実に反映していた。
たとえばグリーンスライムは武器による攻撃がほとんど通用せず、炎に弱く、毒攻撃を繰り出してくる「強いとは言えなくてもめんどくさいモンスター」として登場し、その上位モンスターにあたるグレイウーズにはちゃんと武器攻撃が通用する。ドラゴンはそれぞれのカラーに合った属性ブレスを吐き、コカトリスに攻撃されると石化した。ビホルダーがデスで攻撃してくるのは言うまでもない。
加えて、『ファイナルファンタジー』のモンスターの出現テーブルが良い雰囲気だったことは、もっと知られてもいいと思う。
わずかに先行する『ドラゴンクエストII』でも、海上やロンダルキア洞窟の最下層のモンスターの出現テーブルには雰囲気があったが、それでも個々のダンジョンごとに出現テーブルの雰囲気が大きく異なっていることはなく、たいていは色々なタイプのモンスターがまんべんなく出現した。対して『ファイナルファンタジー』では海上はもちろん、ダンジョンやその階層ごとに出現するモンスターの雰囲気がかなり変わる。
こうしたことをゲーム前半で特に意識させられるのは、土のクリスタルの対リッチ戦、アースの洞窟攻略のあたりだ。土のクリスタルがリッチによって遮られているため、アースの洞窟の周辺の土も腐っていて、そのため、周辺フィールドではアンデッドモンスターが大量に出現する。洞窟に入っていくとアースエレメンタルなど、アースの洞窟らしいモンスターが混じるようになり、たぶん、一度は石化で全滅するだろう。この、ダンジョンやフィールドごとにモンスターの出現テーブルを変え、「いかにもな雰囲気」をつくりだす点にかけて、『ファイナルファンタジー』は巧かった。モンスターの出現テーブルに加えて、戦闘画面のバックにダンジョンのグラフィックが表示されるのも雰囲気を醸し出すのに役立っていただろう。今日のRPGでは標準的なことかもしれないが、そういうことを私が最初に意識したRPGは『ファイナルファンタジー』だったと思う。
『D&D』っぽいことが優れたRPGの必要条件ではない。実際、『ドラゴンクエスト』『ザナドゥ』『女神転生』などはそこまで『D&D』に寄せていないが傑作ではある。それでも、当時のゲーム小僧にとって『D&D』に似ていることは「本格派」っぽく感じられる要素のひとつだったし、『ファイナルファンタジー』はそこらへんをうまく生かしつつ、内実としては遊びやすく、美しく、雰囲気満点のゲームとして遊ばせてくれた。インターフェースの入力スピードも悪くなかったし、魔法攻撃のキラキラしたエフェクトや武器攻撃の描写も美しかった。
本格派ファンタジーの世界にとどまらないどこかへ
他にも長所があるかもしれないが、きりがないのでもうやめよう。最後に『ファイナルファンタジー』のSFっぽさ?について書いてみる。いや、ただのファンタジーRPGじゃありませんよ感というか。
はじめそれは、「飛空石」「飛空艇」というかたちで始まった。さきほど書いたように、『ファイナルファンタジー』は魔法体系や攻撃判定やモンスターの出現テーブルからいって、本格派ファンタジーRPGっぽい装いで始まる。その典型が先に挙げた土のクリスタルの対リッチ戦で、そうした雰囲気は、ファイヤーエレメンタルやレッドドラゴンの潜むグルグ火山にも、ウィンターウルフやホワイトドラゴンが襲ってくる氷の洞窟にも引き継がれている。
……なのだが、ストーリーは滅んだ先進文明の話へと向かっていく。ロゼッタストーン。ルフェイン人の町。そしてミラージュの塔と浮遊城へ。そうこうするうちにファンタジーRPG風のモンスターに混じって、古代文明の機械兵も襲ってくるようになる。
別に、機械のモンスターだけなら当時もさほど珍しくなかった。『ドラゴンクエスト2』にはメタルハンターとキラーマシーンがいたし、『ザナドゥ』にはCZ-812CEがいた。でも、それらは数あるモンスターのバリエーションとして登場したに過ぎず、先進文明の世界に立ち入っていくことをプレイヤーに自覚させるための小道具として登場したわけではない。ストーリーの演出道具としてモンスターの出現テーブルやダンジョンの描写を利用する点にかけても、『ファイナルファンタジー』は一歩先を行っていたように思う。浮遊城はどこからどうみても宇宙船で、実際、エンディングではルフェイン人の文明は優れた技術を持ちながら滅んだと語られる。そうしてカオスとの戦いは時空を超えたものになっていく。
ストーリー・ダンジョン描写・モンスターの出現テーブル等々をとおして、『ファイナルファンタジー』は純然たるファンタジーの物語から、少なくともそうでない物語へと変わっていった。それをSFと言って良いのか私にはわからないし、飛空艇や浮遊城は『天空の城ラピュタ』っぽくもある。ただ、地方のゲーム小僧だった私はこのストーリー展開にびっくりして、それをとても楽しんだ。
ちなみにカオスとの戦いの最終対決に至っても『ファイナルファンタジー』のモンスターの出現テーブルは素晴らしくて、土・火・水・風の階層のモンスターたちはそれらしい雰囲気を帯びていた。*4。
SF愛好家にとって、『ファイナルファンタジー』のこうした一面は先行作品からのパクリでしかないのかもしれない。が、そもそも初代『ファイナルファンタジー』は色々なジャンルの色々な先行作品から色々なものを組み合わせたキメラみたいな作品で、その一部がちょっとSFっぽかったってことなのだろう。
でもこのちょっとSFっぽいという要素が、冒頭リンク先でも記されたように、案外、その後のファイナルファンタジーシリーズの性質を決定づけたのかもしれない。ファンタジーRPGっぽさを大切にしつつも機械やテクノロジーの要素も取り入れ、両方の混じった世界を描くことにかけて、『ファイナルファンタジー』シリーズは卓越していた。その兆しは初代の時点でもう準備されていて、それが当時のゲーム小僧としての私に刺さったのだと思う。『ファイナルファンタジー』がそういう刺さり方をしたゲーム小僧は、たぶん私だけじゃないはずだ。
初代『ファイナルファンタジー』はとても楽しいゲームでした。十代のはじめの多感な時期にあのゲームに出会えたことを、とても嬉しく思います。
*1:追記:D&Dはアメリカ産のTPRG、テーブルトークRPGの一種。ゲームシステム、モンスター、魔法、等々でさまざまなコンピュータゲームにも影響を与えていてたとえば『ウィザードリィ』にもかなりの影響がみてとれる。TRPGとしてなお現役で新しいバージョンもリリースされている。以前、関連する記事も書いたのでそちらも参照 https://p-shirokuma.hatenadiary.com/entry/20240208/1707399000
*2:この感じ方は、完全に当時がTRPGブームで『D&D』がそのなかで雛型的存在だったことに由来している。その文脈を無視すると、これはピンとこない感じ方だろう。
*3:エキスパートセットやコンパニオンセットやマスタールールセットなどのこと
*4:そのなかで最悪だったのがグリーンドラゴンの集団だ。グリーンドラゴン集団が初代ファイナルファンタジーでは最強で、次点が、ダークウィーザードやマインドフレイアの集団だと思う。