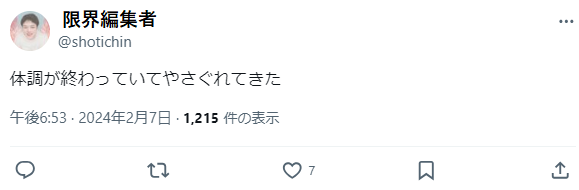president.jp
リンク先の文章は、前半はほぼ拙著『人間はどこまで家畜か』からの抜き出しで、とにかくも社会や環境が進歩した結果として精神医療のニーズは高まっていて、たとえばSSRIのようなセロトニンを補う薬が必要とさいれたり、ASDやADHDといった神経発達症の人に治療なり支援なりが必要な時代になっているよね、と書いた。
いっぽう後半パートは拙著からの抜き出しではまとめきれず、記事におさまるよう書き直した。ここは本当はもっと長い文章にしたかったところで、拙著では編集者さんにお願いして7頁を割いて論じている。それでもまだ、もっと調べてみたい気持ちは残っているし、医療現場と世間のギャップを思い浮かべると、いろんなことを考えずにはいられなくなる。
「それって本当にインクルーシブなんですか」という疑問
この文章では、「その支援って本当にインクルーシブなんですか?」という問題意識をとりあげてみたい。
今日、精神医療の領域でも教育の領域でも、障碍者支援はさまざまに整備され、広く浸透している。例を挙げるなら、発達診断の早期診断・早期支援が行われるようになったり、特別支援教育の対象となる児童生徒が増えたり*1したのは、ニーズに合った支援が実践されるようになり、かつてはザル同然だった支援の網の目がそれなり細やかなものになったことを示していると思う。
そうした支援の輪が広まることは、原則論としては良いことのはずである。そして発達障碍者支援法の第二条の二には、以下のように記されている。
発達障碍者支援法 第二条の二
1 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
2 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
3 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。
地域社会の他の人々との共生。社会的障壁の除去。
こうした理念に基づいて障碍者支援は行われているはず……なのだけど、そうした支援に向けられる目線が、すべて肯定的なわけではない。
建前としては、環境からはみ出してしまう人を障害者差別のようなかたちで排除してはいけないことになっていますし、学校でも職場でもインクルージョン(包摂)が大切とはよく言われるとおりです。しかし実態はどうでしょう? 2022年、障害者権利条約の国連審査が日本に対して行われた際、委員会は日本の特別支援教育を「分離教育」と位置づけ、障害のある子どもがインクルーシブ教育を受ける権利を認識するよう要請しました。
『人間はどこまで家畜か』より
国連の審査員から見た日本の特別支援教育は、インクルーシブなものではないもの、支援を受ける者とそうでない者を分離してしまうものとしてうつっているという。
国内の教育学者からも指摘がある。小国喜弘『戦後教育史』には、文部科学省が推し進めるインクルーシブ教育について、こんなくだりがある。
文部科学省は、2012年に中央教育審議会「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」により、基本的に従来の特別支援教育制度を延長することで対応しようとした。
すなわち、まず「同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である」とした。そのうえで「小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある『多様な学びの場』を用意」することを要諦とした。だがそれは「連続性のある」といいながら、通常の学級と特別支援学級とは別空間であり、さらに地域の学校と特別支援学校とは地理的にも離れている点で、障がい者制度改革推進会議の批判した「原則分離の教育」の継続だった。
小国喜弘『戦後教育史』より
20世紀には、勉強のできない子どもを普通学級から排除して特殊学級に編入し、にもかかわらず障害者教育という大義名分でそれを正当化するような過去があった、その反省のうえに今日の教育制度もできあがっているはずだが、今日の特別支援教育の現状も、体裁こそインクルーシブだが内実はそうとも言い切れない、と疑問を投げかけている。
これと同じ目線で障碍者支援について眺めてみた時にも、大義名分こそインクルーシブでも、実態はそうとも言えない事態に出くわしてしまう。
それが甚だしいのは、2023年に共同通信が報じた、障害者雇用代行ビジネスについての報道だ。
nordot.app
この報道によれば、本来の職場とは別の場所で障害者を雇って働かせる障害者雇用代行ビジネス、本来の職場には障碍者を参加させずに障害者雇用の要件を満たしたことにするためのビジネスが急増しているという。そこで求められているのは、障碍者雇用というインクルーシブな体裁を取りつつ、障碍者を職場から排除し透明化する、そんなニーズだったりしないか?
こうした報道を目にするたび、私は考えこんでしまう。体裁の良いインクルージョンという言葉を表向き成り立たせつつ、それを隠れ蓑に排除や分離が行われているとしたら由々しいことではないか、と。ずるいことでもあるだろう。そして支援する側であるはずの私たちは、このような事態にどこまで抵抗できていて、どこまで加担しているのか? と。
現場が分離・排除・選別を積極的にやろうとしているようにはみえない
他方、精神医療の現場を見ている限り──少なくとも私が実体験してきた現場に関する限り──障害者支援・障碍者雇用の支援者たちが、排除や分離や透明化に積極的に加担しているようには見えず、実践面においてもインクルージョンは目指されているようにみえる。
たとえば障碍者雇用の対象者がどこでどんな仕事をし、どういう収入を得るのかは、そこまで固定的ではない。はじめはA型事業所で働いていた人が、やがて一般企業の障碍者雇用へと変わり、それから一般雇用に変わっていったケースなどは見かけるものである。逆に、一般企業の障碍者雇用で働いていた人が症状再燃し、リハビリの後、A型事業所やB型事業所から再スタートを切るさまに関わることも多い。
こうして職場が変わっていく人をみている限り、もし排除や分離や透明化が結果として存在するとしてもそれは絶対のものではないし、現場の支援者たちが雇用のフレキシビリティや当事者の選択を広げるために払っている努力は相当のものだと言える。
それでも心配りは必要だろう
それでも、インクルーシブであるための諸制度の内側でいつしか分離や排除が行われ、被支援者が透明化されてしまう可能性は、まだなお残る。
くだんの障碍者雇用代行ビジネスのように、それでも制度の抜け穴を見つけてタテマエのインクルージョンを保ちつつ、ホンネの排除や分離を行う動きは存在するかもしれない。少なくともそうした動きが存在する可能性はいつも考えておかなければならない。
そうでなくても、社会全体の構造や世相、制度の仕組みが結果として排除や分離を生んでしまう可能性はあってもおかしくないだろう。私は、個々の現場で努力している人は、悪意や私利私欲に基づいて排除や分離を企てているわけではないと思う。制度設計する人も、現場で支援にあたる人も、原則として善意にもどついて支援や援助に携わっていることをまずは信じるべきだと思う。しかし、個々人がいくら善意に基づいていても結果として分離や排除を内に含んだ支援になってしまったり、分離や排除を内に含んだ構造ができあがってしまうことは全然あり得る。たとえば障碍者支援に際して、私たちはいくらでも「善意に基づいたパターナリスティックな(家父長制的な)」支援をやってしまうことはあり得るが、その際、いくら善意に基づいているからといってその支援が無批判で済ませられるとは、ちょっと考えられない。
支援を行う側の気持ちはさておいて、支援を受ける当事者のなかには、そうした「気が付けば排除や分離を含んだ、けれどもインクルーシブを謳っている諸制度」のなかで前にも後ろにも動けないまま、不承不承、その場に甘んじている人も珍しくあるまい。もちろんそのような当事者の大半は、働く場を変えた時のリスクが大きい、少なくとも一度には変えきれないような諸事情を抱えていることが支援者にも周知されていたりするとは想像しやすいことだ。だからといって、当事者自身の言葉に耳を傾けることをやめてしまい、パターナリスティックな支援に終始しては、結果として排除や分離を含んだ支援に陥ってしまう。
あれこれも排除や分離だと決めつけてしまうのもそれはそれで違う。と同時に、あれもこれもインクルーシブになっていると楽観視するのも、やはり違う。制度も現場も、白か黒かで切り分けられるほど単純なものではない。でも、どんな制度にも大抵は功罪があり、盲点もあり、最もきちんとやっている支援から最もおざなりな支援までのグラデーションがあることを思えば、それでもよく見つめて、よく考えて、よく心配りしておくに越したことはない。そういうことを私なりにもう少し言語化してみたいけれども、これも道半ばだ。
*1:特別支援教育の対象者はH22年の段階で145431人、R2年の段階で302473人となっている