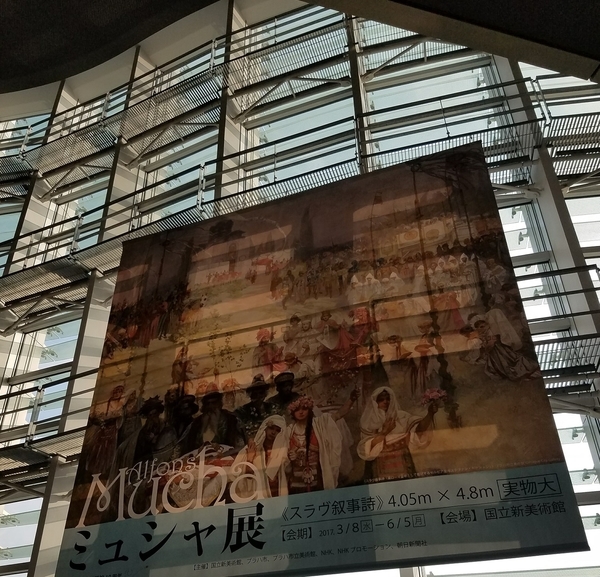II-3 男性にも「ことば」が必要だ – 晶文社スクラップブック
男性から「ことば」を奪っているのは男性自身ではないか - あままこのブログ
上掲リンク先のやりとりを興味を持ちながら眺めた。そこで展開されている、男性に言葉があるかなきか、男女双方がどうやって・どれぐらい抑圧しているのか/されているのかの問題は、私の追求したいテーマそのものではないので、興味のままに文章を追った。
とはいえ、結局この方面で私自身にとって本当に関心があるのは、1.私自身(と私に関わりの深い人々)の利害と表現をどう防備していくのかと、その延長線上の話として、2.その防備のために誰に味方すべきか、といった単純政治の次元で、それより深いレベルの議論は自分には難しそうだった。
で、一連のやりとりを読みながら私が点検したのは、私自身が語る言葉をどれぐらい持っていて、語れそうにない言葉をどれぐらい溜めこんでいるかだ。
あらかじめ前提を述べると、私は、2022年の日本社会でいちおう専門家のライセンスを持った状態で働きながら分泌業、もとい文筆業を兼ねている、そういうホモ・サピエンスの男性だ。典型的ではないかもしれないが、現代社会の男性プレイヤーの一人には違いない。
では、その現代社会の男性プレイヤーである私は、どこまで自分自身について語る言葉を持ち、語れない言葉を抱えているのか?
語る言葉、語れる言葉も結構ある。こういってはなんだが、私は四半世紀ほどインターネット上で文章を書いてきたし、ブログに限っても17年ぐらい書いている。だから自分の言いたいこと、自分のオピニオンを言うことには慣れているほうだ。多くの人に嫌われてでも、問うてみたいことを問うことだってある。
たとえば「オタクだって必ず変わっていくし、必ず年を取っていく」というテーマは私の2005年頃からのお気に入りで、これがはてなブックマーク界隈ではすこぶる不評だが、それでもこれは諸行無常の一端であり、ゆえに真実不虚であるから、これからも私は問い続けることができるし、問い続けるに違いない。
その一方で、私が言えない言葉もたくさんある。
そうした言えない言葉のなかには、くだらないものや益体もないものも多い反面、本当は薄氷の上を歩くような問題だと思っていてもなかなか言えないもの、吐き出せないものも少なくない。いわば、はてな匿名ダイアリーや5chぐらいでしか吐き出せない言葉たち。とはいうものの、それらの場も結局は書いた人間に紐付けられているので、私は匿名っぽいインターネット空間で裸の王様になるほど気楽にはなれない。
男性として・中年としての私のなかに眠っている幾つかの悩み、幾つかの願望、幾つかの不公平感といったものを、もし言葉にしてしまった時、どんなペナルティを受けるのか、どんな詰問を受けるのか、どんな心証変化が起こるのか、想像するのは難しくない。そんな言葉が私の心身にはいくつも眠っている。同年代の女性たち、いや女性全般も男性全般もか、きっと皆もそんな言葉を心身に幾つも眠らせているのだろう、とも想像する。
まさにこれこそが社会からの抑圧とかそういった話とリンクするのだろうけれど、「これを言ったらプレイヤーとしての私の立場がはっきり悪くなる言葉」というのがこの世にはすごく沢山あって、その沢山の語れそうにない言葉たちを束ねているのは、世間の通念であったり、現代の価値観であったり、ときには法や制度だったりもする。語れそうにない言葉を語れそうにない言葉たらしめているのは、正当性を伴った推奨されるべき制約であれ、不当な抑圧としてひっくり返さなければならないものであれ、ともかくも、他者によって構成された社会の側だ。社会のなかでプレイヤーをやっている私は(いや私たちは、か)、社会を眺め、言える言葉と言えない言葉を随時判断している。男性が言えない言葉を作っていることもあれば、女性が言えない言葉を作っていることもあるのかもしれない。けれどもホモサピエンスは男と女という性別にもとづいて世代を紡いできたことを思えば、どちらかが言える言葉/言えない言葉を作っているとみるより、両者の共犯関係や共振関係をこそ検討したくなる。
おっとっと、深入りしそうになってしまった。
いや、そんなことより、とにかく私は、リンク先のベンジャミン・クリッツァーさんとあままこさんのお話を読み、「社会に適応するプレイヤーが、機会主義的に言動を最適化していったら、とりあえずめっちゃ言えない言葉あるよね」みたいなことに思いを馳せたのだった。でもって、その機会主義的に言葉を最適化していることに抑圧を感じると同時に、その抑圧を意識しながらもなお自分の行動を自動的に最適化している自分自身に面白味を感じたりもした。世の人々も、そうやって抑圧を感じると同時に、抑圧があっても自分の行動を自動的に最適化しているとみていいのだろうか。でもって、私のようにそんなオートマチックな所業を面白いと感じたりするものなのだろうか。
プレイヤーとして語れそうにない言葉の多くは、それを語るとプレイヤーとしての私が大小のペナルティを被ると予測される言葉で、かつ、一部は功利主義や危害原理に抵触するから語るべきではなさそうな言葉でもある。もちろん、そういう言葉を語れそうにないとて、そこまで気落ちする必要もない。そういう言葉だったら慎んだほうがいいだろう。
他方、弱音や溜息のような言葉を書ききれない、吐き出せないと感じる場面も結構ある。ブログやSNSやオフラインで、弱音や溜息はどこまで吐き出せるものだろうか。これは年齢や立場や媒体によって異なるはずで、たとえば小学生が友達に向かって吐き出して良い言葉と、四十代も後半にさしかかった男性プレイヤーである私が友達に向かって吐き出して良い言葉はやはり違うだろう。友達ではなく、親だったら、見ず知らずだったら、結婚相手や恋人だったら、と対象を変えてもやはり違うだろう。いずれにせよ、どの場合であっても語れそうにない言葉が存在していて、なぜ語れそうにないかといったら、社会というコンテキストのなかでそれらの言葉を発するとプレイヤーはペナルティを被ることになるからだ。
もし、ペナルティを被らなくても良い立場になれば、語れる言葉も増えるだろう。けれども、およそ、プレイヤーとして計算が必要な現代人は皆、その計算に対応した語れる言葉と語れそうにない言葉をもっているはずで、きっとまあ、今の私に似た思いを持っているのだろうと想像する。
だとしたら、社会のなかで語ってもペナルティにならない言葉を見つけること・作っていくことは重要だし、本来ならペナルティになりかねない言葉を技芸をとおしてペナルティになりにくいかたちで言葉に翻訳していくことも重要ってことになる。
どうせわかりあえないのなら
ここまでを踏まえて、社会と個人、集団と個人、他人と自分の間に必ずあるはずの、語れる言葉・語れない言葉の絶縁に思いを馳せる。社会運動な人なら、この壁を壊せないものか考えるのだろうし、社会学な人なら、この壁について精査するのだろう。で、現代社会の男性プレイヤーの一人としての私は、この壁に面従腹背の姿勢をとりながら、この壁を利用し、この壁に利用されながら、一番うまいことやっていく道を模索するのだろう。
本件に限らず、社会と個人、集団と個人、他人と自分の間にはいつも壁がある。語れない言葉の壁であったり、わかりあえない壁であったり。いや両者はイコールではないがシームレスではあるか。人それぞれに思いと立場があり、思いは伝え合えず、立場は譲り合えず、そうやって大人同士が肩ひじ張りながら生きていくこの世界で、私たちは壁に抑圧されるといいながら壁を使って誰かを抑圧し、壁に塞がれると当時に壁に守ってもらいながら暮らしている。たとえその営為のひとつひとつが、抑圧を、壁を強化する結果になりかねないとしても。
ってことは、わかりあえないし、わかりあわないってことだよね?──それが大人世界の適応を読解する際の、ひとつの前提になり得るというか。
もう少し言葉をポジティブに寄せるなら「お互い、都合の良いところだけわかりあったってことにするのが最適だよね」とでもいうべきか。いやいや、まだちょっとネガティブだな。
人々は、抑圧をなくせ、壁をなくせ、表現の自由を、とか、まあいろんなことを言っている。そうですね。確かにどれも魅力的だ。でもそれだけじゃなく、その抑圧と呼ぶものや壁と呼ぶものにもたれたり、利用したり、道徳サーフィンや正義サーフィンで波に乗りながら生きている側面がある限りにおいて、私たちは本当はわかりあうだなんてことより、わかりあわなくていいから抑圧や壁を駆使して、それらにもたれて生きてもいるわけだ。真にフリーダムな人からみればクソみたいな社会適応と言われそうだが、程度の差と意識/無意識の差こそあれ、現代社会のプレイヤーは多かれ少なかれそうやってもたれて生きている。
こうした話題に際しては、一般に、抑圧なくせ! 壁壊せ! 自由なほうがいい! みたいな話にしたほうが人気が集まって現代社会のプレイヤーとしてクレバーな気がするけれども、じゃ、そのクレバーな人のクレバーな振る舞いも含め、なあ私たちって、世間の通念や現代の価値観や法や制度から自由じゃないし自由であるべきとも思えないし、程度は異なれど、もたれかかっているわけだ。そうしたもたれかかりのゼロな人間がもし現代社会に存在するとしたら、たぶんその人物は危険アナーキストとして早晩刑務所に閉じ込められる気がする。控えめに言っても、その人物が現代社会のプレイヤーとして現前し続けるためには相当なテクニックと才能が必要になりそうだ。
だからまあ、凡夫としての私は、以下のように思わずいられない。
語れそうにない言葉を避けて、抑圧や壁に馴れて、わかったふりしてわかりあえあい・わかりあわない、そんな相互理解の体裁の空中楼閣をつくって、それでお互いプレイヤーやっていきましょう、お互いなるべく不快にならずにわたしたち別々に暮らしていきましょう。永遠に他人のまま、永遠にわかりあえないまま、だけど社会のなかでわかりあっている・コミュニケーションしているという体裁だけを整えて有利取っていきましょう。それがよろしいんでしょう?
そうして小器用に、現代人のプレイヤー然として生きていく。きっとみんなもそうしている。正義や道徳や法にかなっている部分に関しては尚更だ。だけど小さな痛みは残る。痛みは何か。語る言葉をもたないことにしてしまった何かが疼いているからだ。その疼きを言葉にする方法をあきらめ、意志をもあきらめたからだ。そうやって虚勢のように生きていくこと自体が、自分の語れなさ、言葉にできなさをますます強化しているかもしれない。男なら泣くな。いいや、女でも泣くな。泣いてみせたっていいじゃないか。うんうん、現代人のプレイヤーとして、それがそのとき最適な振る舞いならばね。
ああ、おれってこんな中年男性プレイヤーしたかったんだっけ? したかったとも言えるけれども、そうでないとも言える。いずれにせよ私は全裸中年男性にはなれない。2022年の社会のなかで、私は現役の、プレイヤーだからだ。誰の歌だったかな。勝利も敗北もないまま、孤独なレースは続いていく。