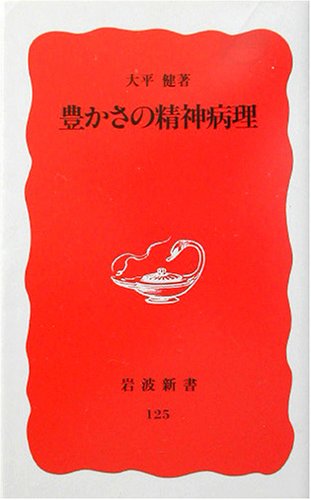anond.hatelabo.jp
作業が一段落した時に、こんなはてな匿名ダイアリーを見つけてきた。曰く、「書評が書けない」と。この「書評はどうすれば書けるのか」の答えは、
・どういう書評を書くのか
・何をもって書評と呼ぶのか
・誰が読むような書評なのか
によって答えが違っているはずで、匿名ダイアリー筆者にていねいにヒアリングをしたうえで「あなたの思うような書評を書くには、これこれ、こういう要素や積み重ねが必要です」みたいに応答するのが一番いいんだろうなと思った。
で、私がこの文章を書き始めたのは、それとは別で、「自分が書きやすい/書きにくい書評とは何なのか」「自分は有名書評ブログのようには書評を書けないのはなぜなのか」、みたいなことを考えこんでしまったからだ。いわば書評する(ことのある)人間としての自分自身を振り返りたくなったので、自分の問題に引き寄せながら書評について考えてみる。
本をダイジェストにできるなら、書評の土台ができているんじゃないか
世間で書評として流通している文章を読むと、どうあれ、それは読者が読んでその本についてわかる内容になっている。

たとえば上の画像は、拙著『何者かになりたい』などの書評が掲載された新聞*1のものだが、新聞の書評は「まだその本のことを知らない人に、本のあらましやセールスポイントや魅力を紹介する」内容になっている。こうした新聞書評の場合、要約能力がものすごく重要になる。なにしろ文字数が少ないのだから、紹介する本のあらまし・セールスポイント・魅力をぎりぎりの密度に詰め込まなければ書評として成り立たないからだ。
そういう意味では、上掲リンク先の匿名ダイアリーの筆者がなにげなく触れていた点がめちゃくちゃ重要だ。
本をうなずきながら読む
読み終わってみたが、とくに書くことがない
おもむろに書き出してみてもダイジェストにしかならない
「ダイジェストにしかならない」とおっしゃっているけれども、本当は、このダイジェスト化が書評では最も重要な能力だと私なら思う。不特定多数が読む前提で書評をアウトプットするなら、その本の魅力や勘所を把握し、要約する能力はものすごく重要だ。もし、匿名ダイアリーの筆者が必要十分なダイジェスト化の能力を持っているなら、それはスキルフルなことだと思うし、どんどんダイジェスト化を尖らせていくだけでも値打ちのあることなんじゃないかと思う。
私が見るに、書評ブログのエキスパートたちは、このダイジェスト化の能力が皆ものすごく高い。もちろん彼らの場合、ダイジェスト化の能力がものすごく高いだけではない。レトリックの機敏にも優れているし、自分の問題や社会の問題に引き寄せてその本の内容を論じることにも慣れている。紹介する本が類似書とどう違うのか、そのジャンルのなかでオーソドックスなのかアバンギャルドなのか、筆者の来歴のなかでどのように位置づけられるのか、等々を考え、判断し、それに対する自分の見解を添えることも多い。
……うーん、こうやって書いてみると人気書評ブログの人ってやっぱりすごいと思う。少なくとも私みたいな中途半端ブログをやっている人間に比べれば、上記のとおりのことをスキルとして、またはシークエンスとしてやっている気配が濃厚だ。でも、そうした特上の花束みたいな書評のベースになっているのは、やはり、精度の高いダイジェスト化の能力だと思う。書評ブログのエキスパートで、そこが弱いブロガーなんて見たことがないからだ。
ダイジェストにする以外にたぶん必要なもの
じゃあ、ダイジェスト化の能力さえ高まればおのずと書評たりえるのか。
ノー、という人もいるかもしれない。
でも、私だったらイエス、と答えたい。
ただ、私がイエスと答えるのは、想定読者をある程度せまくする場合だ。たとえば想定読者を自分自身だけにまで狭めると、書評はダイジェストと自分自身にとっての備忘録になる。
書評ブログではないけれど、私はワイン評のブログを持っていて、これなどはまさにそうだ。
polar-vineyard.hatenablog.com
ここには12年前から現在までに私が飲んだワインのほとんどが載っているが、想定読者が自分自身だけなのでまさにダイジェスト&備忘録になっている。すごく無味乾燥な文章だけど、自分が読んで振り返るぶんにはこれでぜんぜん構わない。
ところが想定読者を広く想定すると、ダイジェストオンリーではたぶん足りない。他人の関心を惹くにはプラスアルファの魅力・要素が必要で、それを削ぎ落したダイジェストの羅列は、上掲ワインブログがそうであるように他人には無味乾燥な寸評になってしまう。
逆に、プラスアルファのその魅力・要素を備えた書評が、ダイジェストの要約が弱くても人気を獲得し、ベテラン書評家の書評をしのぐ勢いで流通することだってありえる(ベテランでもない人の書評は「打率」ではやっぱりベテランに敵わないのだけど)。書評に、個人の執着や怨念や愛情が強く結合し、その結合のぐあいが読み手のシンパシーや反感を呼ぶ場合は特にそうだ。
この、シンパシーや反感を呼ぶような書評の流通術はいちおうノウハウ化されていて、書評する本のことごとくがシンパシーや反感と抱き合わせになっている、という場合だってある。私もあまり他人のことは言えず、 genuine な書評家の人と比べて、私は書評を私の執着や怨念や愛情にかなり寄せているほうだと思う。でもって、 genuine な書評家の人は、たぶん、そういうのあまり良く思っていないんじゃないかなーと想像したりもする。いつかオフラインの集まりで「シロクマさんの書評らしきものは、書評というよりシンパシーや反感ですね」なんて言われたら、顔から汗が噴き出して脱水症状になってしまいそうだ。や、書評がシンパシーや反感に埋没しすぎてしまうのはやりすぎだと、一応私なりの分別はもっているつもりですが。
シンパシーや反感を書評に練り込む際に必要なのは、その本の内容と自分自身との間で起こるなんらかの反応だと思う。ここでいう反応はどういったものでも構わない。腹が立った、びっくりした、疑問が氷解した、10年前に読んだ本の伏線を回収した、世の中でこの本が好評を博しているのが腑に落ちた、等々だっていいのだと思う。そういった、本をとおして自分自身の身に起こったこと、感情や気分に影響されたことが、おのずとシンパシーや反感も含めた、書評を彩るもうひとつの大事な要素になる。
たぶんアニメ評やゲーム評やワイン評でもそうだけど、書評には、書き手と読み手のエモーションがシンクロしたり喧嘩したりすることをとおして読ませる・印象づける側面もあって、新聞書評のようなダイジェスト性の高い書評はともかく、エッセイ寄り書評の場合はこの部分が馬鹿にならないのだと思う。
ダイジェスト化する技術と、エモーションを喚起する技法と
書評にとって重要な要素としてダイジェスト化とエモーションの喚起という二要素について書いてきた。書評の魅力がこの二要素だけから成るなんてことはなく、たとえばユニークな着眼や博覧強記に基づいた本の精査能力なんてのも魅力の一部には違いない。が、そういったものまで触れていると無限に長くなってしまうので省いてしまうことにした。
ダイジェスト化する能力とエモーションを喚起する能力、どちらも大事だが、これらは能力としては性質がかなり違っていて、それを獲得するための方法も違うようにみえる。
読んだ本のダイジェスト化、つまり要約は、練習の方法を間違えなければ、たぶん訓練でなんとかなる。そもそも要約は、小学校時代から宿題やテストのなかに課題として忍び込んでいる。ために、国語の成績が良かった人なら本を要約する能力はだいたい身に付いているはずだ。あとはその方法をテストや課題ではない本に適用できるかどうかで、適用してしまえば、書評のうちダイジェスト化の部分は何とかなるんじゃないだろうか。
国語の課題をとおして広く伝授されている様子をみるに、要約は、書評を支える能力群のなかでも技術としての側面の強い、比較的再現可能な、そういう性質のものなのだと思う。
対して、読んだ本をとおしてエモーションを喚起する能力は、再現可能性があまりなさそうにみえる。いちおうノウハウ化され、言葉遣いやレトリックまでは再現可能……のようにみえて、まさにその言葉遣いやレトリックのクセというかフックというかが属人的で、うまい人はうまく、へたな人はどうにもへただ。エモーションを召喚するための感受性もまた然り。ものすごい量の本を読み、文章読解能力に優れた人でも、エモーションや感受性の面ではさっぱり……ということは珍しくない。
だからエモーション喚起能力は技術(テクネー)というより技法(アート)、と言い換えられるかもしれない。天分に恵まれていない人は、無理をして身に付けようとしないほうがいいんじゃないかと思う。それより、訓練でなんとかなるダイジェスト化のほうで功夫を重ね、手堅い書評を手堅く上達させていくほうがうまくいくんじゃないだろうか。
こうやって整理したうえで我が身を振り返ってみると、私は良くも悪くもエッセイ寄り書評、いや、エッセイ大好き人間のように思われ、今のブログライフは身のほどにすごく合っている気がした。本を読み、ブログを読み、人や社会を読み、自分自身のエモーションを召喚したうえで何かを書くこと自体がとても楽しい。そのためにブログをやっているようなものだとも思う。
そのエモーションの源泉は何かと説明するのは難しいけれども、たぶん、週末に猫をモフって過ごすようなところからエモーションは生じるのだと思うので、日々の暮らしのなかで、文章を書くのにちょうどいいようなエモーションを調律していくのが今の自分に必要なことだと、この作業をとおして再確認した。
*1:上毛新聞、10月3日朝刊。丸ごと読めちゃうのはまずいかと思い、一部、ぼかしを入れておきました。